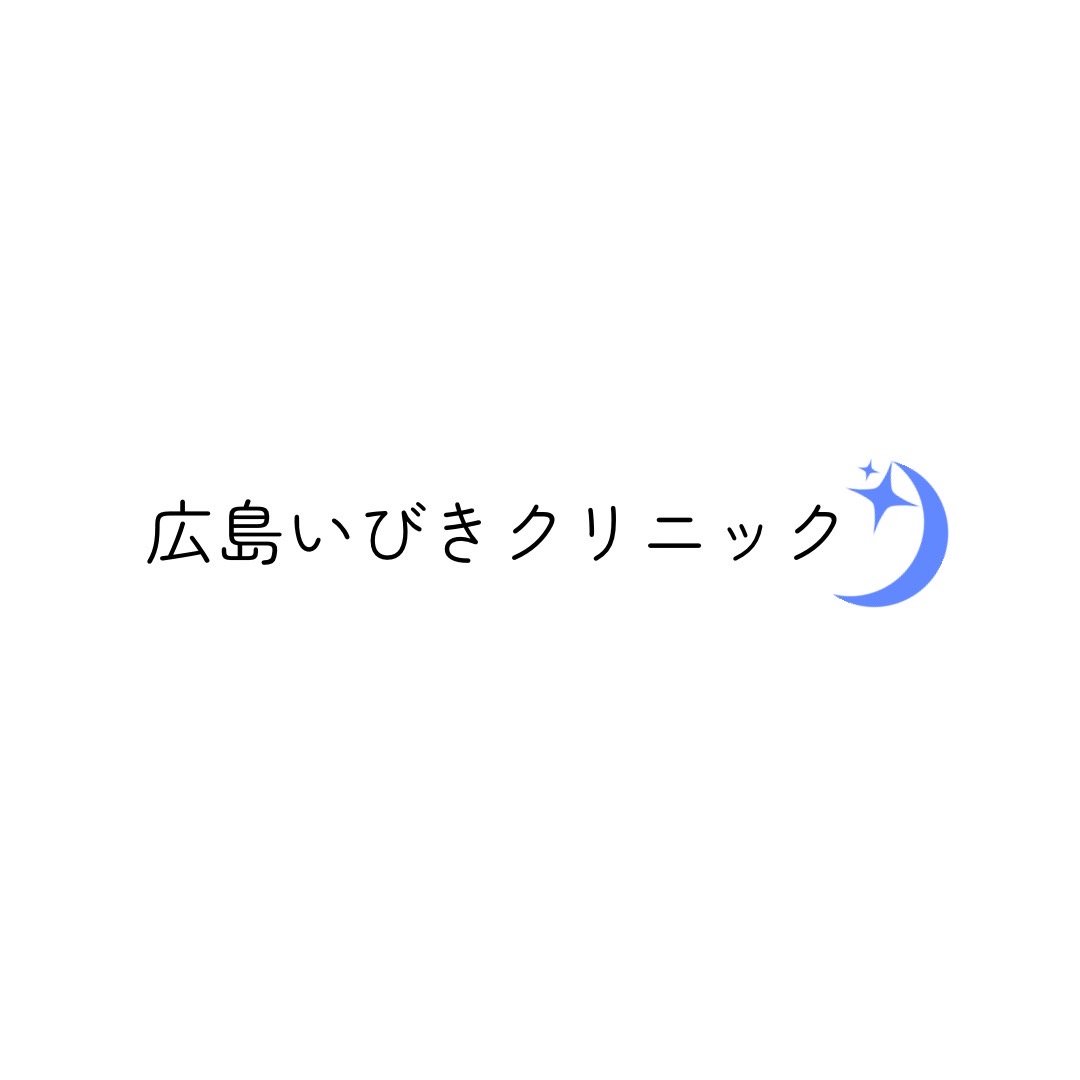睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは?
睡眠中に呼吸が止まる病気
睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が繰り返し一時停止してしまう病気です。眠っている間に何度も呼吸が止まるため、熟睡が妨げられてしまいます。多くの場合はいびきを伴い、息苦しさから夜中に何度も目が覚めることもあります。その結果、日中に強い眠気や倦怠感、集中力の低下が現れ、生活に支障をきたすようになります。
気道がふさがる主な原因
睡眠時無呼吸症候群の多くは「閉塞型」と呼ばれ、喉や鼻の空気の通り道(気道)が物理的に塞がってしまうことで起こります。代表的な原因の一つは肥満で、太って首まわりに脂肪がつくと喉の内側が狭くなり、睡眠中に舌や軟部組織が下がって気道を塞ぎやすくなります。また、下あごが小さいなど骨格上の問題がある人も、わずかな体重増加で気道が狭まり無呼吸のリスクが高まります。そのほか、慢性的な鼻づまり(鼻炎・副鼻腔炎)や扁桃腺・アデノイドの肥大、大きな舌なども、睡眠中に気道を狭くして無呼吸を引き起こす原因になります。
日本人は睡眠時無呼吸症候群になりやすい?
実は、日本人を含むアジア人は欧米人と比べてSASを発症しやすいと言われています。理由は顔や顎の骨格の違いにあります。一般的に東洋人は顔に凹凸が少なく扁平で、上顎に対して下顎が小さい傾向があり、この骨格だと喉や鼻の奥の空間が狭いため肥満でなくても気道が塞がりやすいのです。欧米では主な原因が肥満ですが、日本人では骨格の特徴が大きく影響し、「太っていないのに無呼吸症候群になる」というケースも少なくありません。つまり、日本人は体質的にSASのリスクを抱えやすいと言えるでしょう。
睡眠時無呼吸症候群は顔つきが変わる?主な特徴

小さなあごや面長など骨格の特徴
睡眠時無呼吸症候群の患者には、下あごが小さい(あるいは顔が細長い)といった骨格の特徴が見られることがあります。こうした顔立ちの人は喉の奥の空間がもともと狭く、寝ている間に気道が塞がりやすいのが特徴です。例えば下顎が小さいと舌の収まるスペースが不足し、仰向けで寝たときに舌の根が喉に落ち込みやすくなります。顔が面長で顎がほっそりした人も同様に気道が狭いため、わずかな要因で無呼吸を発症しやすくなります。日本人にもこうした骨格の方は多く、肥満でなくてもSASの一因となり得ます。
扁桃腺やアデノイドが大きく口呼吸しやすい顔立ち
扁桃腺やアデノイドが肥大している人は、鼻呼吸がしづらいため常に口で呼吸しがちです。その結果、口元がぽかんと開いた顔立ちになり、下顎の発達が不十分で顎が後退気味になります。さらに舌の位置が下がる影響で顎下に脂肪がつきやすく、二重あごになったり顎と首の境目がわかりにくい丸顔になる傾向があります。こうした特徴は「アデノイド顔貌」と呼ばれ、長期間の口呼吸によって骨格や表情に現れた変化です。
鼻づまりや副鼻腔炎による腫れぼったさ
慢性的な鼻づまり(副鼻腔炎や慢性鼻炎など)があると、顔が腫れぼったく見えることがあります。鼻から十分に呼吸できないため無意識に口呼吸になりやすく、それが夜間のいびきや無呼吸につながる可能性があります。一見すると鼻の不調と顔つきは睡眠と無関係にも思えますが、鼻呼吸ができない状態が続くと睡眠の質が低下し、結果的に顔のむくみや表情の変化を招くことがあるのです。
合併症によるむくみ・ゆがみ
睡眠時無呼吸症候群を長期間放置すると、脳卒中や心不全など命に関わる合併症を引き起こし、それによる顔つきの異常が現れる場合もあります。例えば脳卒中で片側の顔面神経が麻痺すると、口元が歪んで左右非対称な表情になります。また、心臓の機能が低下すると全身にむくみが生じて、特にまぶたや顔が腫れぼったくなることがあります。これらはSASそのものが顔を変えるというより、SASが招いた重大な合併症の症状として表れているものです。
口呼吸や睡眠不足による顔色の悪さ・クマ
慢性的な口呼吸や睡眠不足は顔色にも影響します。常に口で呼吸していると唇や喉が乾き、酸素の取り込みも不十分なため、血色が悪く肌がくすんで見えがちです。さらに熟睡できていないと目の下にクマができたり、まぶたが重たく垂れたりします。実際、SAS患者は「疲れて見える」「実年齢より老けて見える」と評価される傾向がありますが、治療によって十分な睡眠が取れるようになると顔色やクマが改善し、表情にも明るさが戻ることが期待できます。
あなたは睡眠時無呼吸症候群?日常でできるチェックポイント

口呼吸や二重あごは無呼吸のサイン
日常生活の中で、自分が睡眠時無呼吸症候群ではないかと疑う手がかりになるサインがあります。まず、口呼吸の習慣です。日中いつも口が開いている、朝起きると喉や口の中が乾いている、といった場合は寝ている間も口呼吸になっている可能性が高く、無呼吸のリスク要因になります。次に、二重あごも要チェックです。あまり太っていないのに顎下に脂肪がついて二重あごになっている人は、下顎が小さく喉の気道が狭い骨格である可能性があります。また、首が短く太い印象の場合も気道周囲に脂肪や軟部組織が多く、喉が塞がりやすい体型と言えます。こうした特徴に心当たりがあるなら、無呼吸のサインかもしれません。
睡眠中にいびきの後に呼吸が止まるのは要注意
睡眠時無呼吸症候群では、「大きないびきの後にしばらく呼吸が止まる」という典型的な症状が現れます。本人は気づきにくいですが、家族や同室者が観察すればわかります。典型的には、ぐうぐうと大きないびきをかいた後に突然しんと静かになり(呼吸が停止し)、しばらくしてから「ガッ」と息を飲み込むような音とともに呼吸が再開します。もし家族から「いびきが途中で止まって苦しそうだった」と指摘された場合は要注意です。また、睡眠中に苦しそうな表情をしていたり、頻繁に寝返りを打って落ち着かない様子が見られる場合も、無呼吸を疑うポイントになります。
日中に強い眠気や集中力低下が見られる
夜間の無呼吸は翌日の日中の状態に影響します。十分な睡眠時間をとっているはずなのに、日中に強い眠気が襲ってきたり、少しソファに座っていると居眠りしてしまうといったことはないでしょうか。車の助手席に乗った途端に寝てしまう場合も、夜の睡眠の質が低下しているサインです。また、朝起きたとき頭が重い、寝ても疲れが取れない、日中にイライラしやすい・集中力が続かないといった症状も、SASによる慢性的な睡眠不足が原因かもしれません。心当たりがある場合は、一度専門の検査を受けてみることをおすすめします。
顔のむくみやクマ、首まわりの変化も手がかりになる
見た目の変化にも注目しましょう。最近、顔がむくみやすくなった、朝起きるとまぶたが腫れて目の下にクマができていると感じる場合、睡眠不足や無呼吸の影響が考えられます。慢性的な睡眠不足は血行不良やホルモンバランスの乱れを招き、顔色が悪くクマが目立つ原因となります。また、首や顎まわりが以前より太くなった、顎下に贅肉が付いて輪郭が変わってきた、といった体型変化もSASリスクが高まっているサインです。こうした外見の変化と日中の眠気やいびきの症状が重なる場合は、早めに医療機関で検査を受けましょう。
睡眠時無呼吸症候群を放置するとどうなる?合併症リスク
心筋梗塞や脳梗塞のリスク
睡眠時無呼吸症候群を治療せずに放置すると、重大な心血管系の合併症リスクが高まります。なかでも注意すべきは心筋梗塞(心臓発作)や脳梗塞(脳卒中)です。睡眠中に無呼吸で体内の酸素が不足すると、そのたびに交感神経が刺激されて血圧や心拍数が急上昇し、血管や心臓に大きな負担がかかります。この状態が続くと動脈硬化が進行し、SAS患者はそうでない人に比べて脳卒中や心筋梗塞を起こす確率が格段に高くなることが明らかになっています。命に直結するリスクが潜んでいる点で、SASを甘く見るのは危険です。
高血圧や不整脈など生活習慣病との関係
睡眠時無呼吸症候群は、高血圧や不整脈などの生活習慣病とも深い関係があります。無呼吸による酸素不足と睡眠分断が続くことで体が慢性的なストレス状態になると、血圧が常に上がりやすくなります。実際、SAS患者には高血圧を合併する例が多く。心房細動などの不整脈もSASでは頻繁に見られます。睡眠中に呼吸が止まると心臓に負担がかかり、心拍リズムが乱れやすくなるためです。SASは単なる睡眠の問題ではなく、全身の健康に影響を及ぼす病気なのです。
睡眠時無呼吸症候群のセルフケア

生活習慣を整えて体重をコントロール
睡眠時無呼吸症候群の改善には、まず基本となる生活習慣の見直しが重要です。特に肥満がある場合は減量に取り組みましょう。適度な食事制限とバランスの良い食生活、そして無理のない範囲での定期的な運動を習慣づけ、適正体重の維持を目指します。首や顎周りについた余分な脂肪が減れば、喉の気道が広がり無呼吸の発生頻度が大きく低減します。また、就寝前のアルコールや喫煙は喉の筋肉を弛緩させ無呼吸を悪化させる要因となるため控えましょう。
横向きに寝て気道を確保する
寝るときの姿勢を工夫するだけでも、いびきや無呼吸が改善することがあります。仰向けで寝る習慣がある人は、意識して横向きで眠るようにしてみましょう。仰向けでは舌や軟口蓋が重力で喉の奥に沈み込みやすく、気道を塞ぎがちです。一方、横向きで眠れば喉への沈下が起こりにくく、無呼吸の頻度が減ることが期待できます。横向き寝に慣れない場合は、抱き枕を使うなどして体勢を整えると良いでしょう。
マウステープなど鼻呼吸を促すための工夫
睡眠中の口呼吸を防ぎ、鼻呼吸に誘導する工夫も効果的です。市販の「口閉じテープ(マウステープ)」を寝る前に口に貼って唇を閉じておくと、強制的に鼻呼吸に切り替えることができます。口呼吸によるいびきや無呼吸が軽減するケースは多く、手軽に試せる対策です。ただし、重度の鼻づまりがあるときは無理せず、また既に無呼吸症候群で治療中の場合は主治医と相談のうえで使用しましょう。寝ている間になるべく鼻呼吸ができる環境を整えることが大切です。
口まわりや舌の筋肉を鍛える体操
喉や舌の筋肉を鍛えて気道のゆるみを改善するトレーニングもあります。例えば「あいうべ体操」という簡単な体操があります。口と舌の筋力アップを目的とした運動で、「あー」と大きく口を開け、「いー」と口角を横に広げ、「うー」で唇を前に突き出し、「べー」で舌を前下方に突き出すという一連の動きを行います。これを毎日繰り返すことで舌や喉周りの筋肉が鍛えられ、口呼吸やいびきの改善につながるとされています。寝る前の数分間などに継続して行うことが大切です。
医療機関で行う主な治療法

マウスピース療法
軽症から中等症の睡眠時無呼吸症候群には、歯科で作成するマウスピース(口腔内装置)療法がよく用いられます。就寝時にマウスピースを装着して下顎を前方に少し移動させ、喉の気道を広げる治療法です。下顎が前に出ると舌の付け根も引き上がり、仰向けに寝ても気道が塞がりにくくなります。機械を使わない手軽な治療法ですが、フィッティングのため歯科での型取りや調整が必要です。また、使用開始直後は顎に違和感を覚えたり、長期使用で歯並びに変化が生じる可能性もあります。正しく使えば症状の大幅な軽減が期待できます。
CPAP(シーパップ)治療
中等症以上の睡眠時無呼吸症候群には、CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)療法が最も有効です。CPAP装置は小型の空気ポンプとマスクからなり、就寝時に鼻(または鼻と口)にマスクを装着して使用します。機械が一定の空気圧を送り込み、喉の気道を内側から押し広げた状態を保つことで、睡眠中の無呼吸や低呼吸をほぼ完全に防ぐことができます。CPAPを毎晩正しく使用すれば、夜間の酸素低下やいびきが解消し、多くの患者さんで日中の眠気や体調も大きく改善します。デメリットは毎晩マスクを着ける煩わしさや機器の管理ですが、それを差し引いても重症SASでは第一選択となる治療法です。
咽頭口蓋形成術
無呼吸の原因が喉にある場合、外科手術の「咽頭口蓋形成術」で治療することもあります。全身麻酔下で軟口蓋や口蓋垂、肥大した扁桃を切除し、喉の空間を広げる手術です。一定の効果が報告されていますが、侵襲が大きく術後の喉の痛みや出血リスクも伴います。また、時間の経過とともに無呼吸が再発するケースもあり、特に体重が増えると再発しやすくなります。他の治療(CPAPやマウスピース、減量など)で効果が不十分な場合の選択肢となります。
レーザー治療
メスを使わずレーザーで喉の組織を縮小させる「レーザー治療」もあります。レーザー口蓋垂軟口蓋形成術(LAUP)といい、局所麻酔下で軟口蓋や口蓋垂の一部をレーザー照射で焼き縮め、組織を引き締める方法です。切開手術に比べ出血が少なく日帰り可能な点がメリットで、軽症のいびき改善を目的として行われます。ただし、重度のSASに対してレーザー治療単独で根本改善を図るのは難しく、現時点で標準的治療とは言えません。軽症例や他治療の補助的な選択肢にとどまりますが、切らない治療で負担が少ない治療法です。
まとめ|改善が見られない場合は早めに専門医へ相談を
睡眠時無呼吸症候群は放置すれば健康に深刻な影響を及ぼしますが、適切な治療で改善が期待できる病気です。本記事で述べた顔つきの特徴や日常のサインに心当たりがあれば、自己判断せずに早めに専門医に相談しましょう。耳鼻咽喉科や睡眠クリニックで検査を受ければ、正確な診断と適切な治療法の提案が得られます。セルフケアで改善が見られない場合はもちろん、少しでも不安があれば躊躇せず専門家の力を借りることが大切です。早期発見・早期治療によって、いびきや無呼吸による日常生活への支障が減るだけでなく、顔つきも改善していくでしょう。家族の指摘や自分の直感を大切にして、快適な睡眠と健康を取り戻す第一歩を踏み出してください。